私は東京医科歯科大学の歯周病専門外来にて、難症例を含む幅広い治療の研鑽を積み、その後は都内歯科医院にてお子さんからご高齢の方まで多くの患者様のお口の健康づくりをサポートしてまいりました。
患者様一人ひとりの症状やご希望に合わせて、あらゆる治療の選択肢をご提案し、心から納得していただける治療法をお選びいただけます。神保町ミセ歯科・矯正歯科は、患者様との信頼関係を大切に築きながら、ドクター・スタッフともに一丸となって、あなたの健康を末長く支えてまいります。
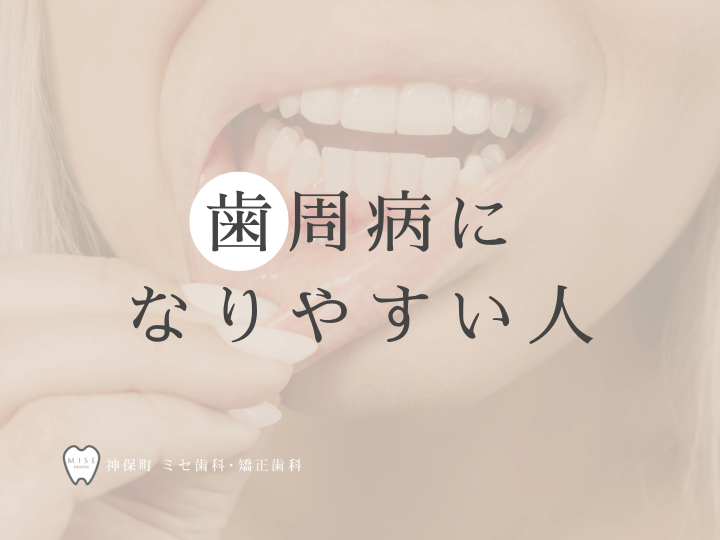
歯周病は、誰もが罹患する可能性のあるお口のトラブルです。「大したことはないだろう」と思う方も多いかもしれませんが、放っておくと、糖尿病や心筋梗塞などを引き起こすリスクもあります。 もちろん、適切にケアをすれば十分防げる疾患でもあります。お口はもちろん、全身の健康を守るためにも、正しい予防法を知り、実践しましょう。
この記事では、歯周病の基本知識から、特に罹患するリスクが高い人の特徴、さらには予防策や専門医が推奨する正しい歯磨き方法までを詳しく紹介します。
ご自身の健康を守るためにも、ぜひ参考にしてください。
歯周病とは
歯周病は、歯ぐき(歯肉)や歯の骨(歯槽骨・しそうこつ)などの歯を支える周辺組織が炎症を起こす病気です。
初期段階では自覚症状がほとんどないため、知らないうちに悪化することがあります。早期発見のためにも定期的に歯科検診を受診することがとても大切です。
また、適切にケアをすれば予防できる疾患でもあるため、正しい歯磨き方法やケア方法を知っておきましょう。
歯周病の症状と原因
歯周病になると、その初期には歯ぐきに次のような症状がみられます。
- 赤み
- 腫れ
- 出血
さらに悪化すると、口臭がするほか、歯の骨が溶け、最悪の場合、歯が抜けてしまう可能性もあります。
歯周病の原因は、プラークです。これは、歯の表面や歯と歯の間に付着している細菌の塊をいいます。口腔内のケアが十分に行き届いていないために、細菌が増殖し、形成されます。
また、歯周病は日本人が歯を失う原因として、第1位に挙げられる病気です。高齢になるほどそのリスクが高まるため、注意が必要です。
歯周病になりやすい人の特徴
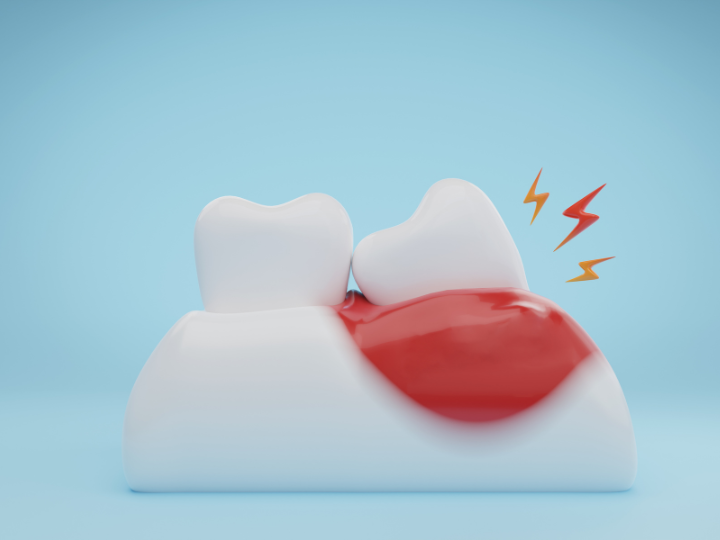
次の特徴がある方は歯周病になりやすいため、特に注意しましょう。
正しい歯磨きができていない人
正しく歯磨きができないと、歯や歯と歯ぐきの間にプラークが溜まりやすく、細菌が増殖しやすい状態になります。炎症が起こり、歯周病になる可能性が高いといえます。
また、プラークを放置すると、石灰化して歯石になります。さらに多くの細菌を集めて歯肉の炎症を促進し、歯周病はさらに進行してしまうのです。
甘いお菓子をよく食べる人
虫歯菌は糖分をエサにして増殖するため、甘いお菓子を食べた後の口腔内は、プラークが形成されやすい状態にあります。細菌の増殖に適した環境であるため、歯周病を発症するリスクは高いといえます。
また、甘いお菓子は粘着性があるものも多いものです。歯の表面に付くとなかなか取れにくいため、細菌が増殖しやすい環境が長時間続くことになってしまいます。そのため、甘いものをよく食べる人は、歯周病になりやすいのです。
歯並びが良くない人
歯並びや咬み合わせがよくないと、凹凸があるために隅々までブラッシングができず、プラークが蓄積しやすくなります。また、食べかすが歯間に挟まりやすいことも、プラークができやすい原因の一つです。
細菌が繁殖しやすい環境であるため、正常な歯並びの人よりも歯周病のリスクが高いといえます。
妊娠中の人
女性は妊娠すると、「プロゲステロン」と「エストロゲン」という2つのホルモンの分泌が増えます。これらのホルモンは、口腔内にいる一部の細菌の栄養源にもなるため、細菌が増殖しやすくなってしまいます。
さらに、妊娠中は唾液の分泌量も減るものです。そのうえ、つわりがひどいために、歯ブラシを口にすることすら難しい方もいます。通常よりも口腔内の環境が悪化しやすいため、歯周病や虫歯になる方も多いのです。
糖尿病に罹患している人
糖尿病に罹患した人は、血糖値だけでなく、唾液に含まれる糖分の濃度も高いものです。さらに、唾液の分泌量が少ないため、プラークが形成されやすい傾向があります。そのため、健康な人より歯周病になるリスクも高いのです。
年齢別!歯周病罹患率

年齢ごとの歯周病の罹患率は次のとおりです。
| 年齢 | 歯周病罹患率 |
|---|---|
| 15〜24歳 | 20% |
| 25〜34歳 | 30% |
| 35〜44歳 | 40% |
| 45〜54歳 | 50% |
| 55歳以上 | 55〜60% |
年齢が高くなるにつれ、その罹患率は高まることがわかります。特に45歳以上になると、半数の方が発症します。予防のためにも、30代後半頃から、歯医者でそのリスクを調べてもらい、ケアをしっかりおこなうのが望ましいところです。
意外と多い!実は歯周病リスクを高める日常の習慣
次のような習慣がある方は、歯周病になるリスクがより高いといえます。予防のためにもできる限り改善しましょう。
タバコをよく吸う人
喫煙者は歯周病にかかりやすいだけでなく、重症化しやすく、治りにくいため、特に注意が必要です。タバコを1日10本以上すうと、歯周病にかかるリスクは5.4倍にもなるといわれています。
その原因は、タバコに含まれる有害物質が、口内の細菌バランスを崩し、プラークの形成を促進するからです。
また、血管の収縮によって血流が悪化するため、酸素や栄養素の供給が減少し、自然な治癒力が低下します。その結果、細菌感染への抵抗力も弱まってしまい、歯周病を発症してしまうのです。しかし、血流悪化のために出血やはれが起こりにくいため、初期症状が見られず、発見は遅れてしまいます。
免疫力も低下するため、治療をしても治りにくく、手術後の回復も遅れます。
歯ぎしりや食いしばりがひどい人
歯ぎしりや食いしばりがひどいと、歯周病の発症だけでなく、その進行も速めます。
歯ぐきや骨に長時間、強い力が加わるために、歯周組織がダメージを受けて炎症を起こしやすく、歯周病の発症につながってしまうのです。さらに、強い圧力によって、歯ぐきの腫れや出血、歯を支える骨(歯槽骨)の破壊も進みやすく、歯周病が進行しやすくもあります。
口呼吸が癖になっている人
常に口呼吸をしている人も注意が必要です。口呼吸が常態化すると、唾液の分泌量が減るために、口腔内が乾燥しやすくなります。唾液には、口の中の汚れを洗い流すほか、酸を中和したり、細菌の増殖を抑えたりする役割がありますが、乾燥した状態では、その効果を得られません。口の中の健康が守られず、歯周病を発症してしまうリスクが高いのです。
歯周病にならないための予防法

歯周病を予防するには、次のことを実践するのが有効です。
定期的に歯科クリニックで検診を受ける
歯科クリニックでの定期検診の受診は、歯周病の予防に大変効果的です。
検診だけでなく、口腔内の状態に合わせたブラッシングの指導を受けたり、歯磨き粉の選び方、フロスや歯間ブラシの使用方法を教えてもらったりもできます。同時にクリーニングを受ければ、プラークや歯石の除去など普段のブラッシングでは難しいケアもしてもらえるので、歯周病のリスクをより低減できます。
万が一、歯周病を発症していても、適切な治療を速やかに開始すれば、重症化はしません。
歯周病やそのリスクの早期発見によって、ご自身の負担を大きく減らせるのです。
正しい歯磨き習慣を身につける
歯周病を引き起こす細菌は、歯垢の中にいます。そのため、食後は正しい方法で歯磨きをし、できる限り口の中に歯垢を残さないようにすることが大切です。
特に、ブラッシングの際には、歯と歯ぐきの両方を磨くことを意識してください。歯磨きの主な目的には、以下の二つが挙げられるからです。
- 歯の表面に付いた汚れや歯と歯の間にある歯垢を落とすこと
- 歯ぐきをマッサージし、血行を促進して、歯肉炎を改善すること
このように歯と歯ぐきでは、ブラッシングの目的が違うため、次のようにアプローチを変えることが大切です。
| ブラッシングする部位 | ポイント |
|---|---|
| 歯、歯間 |
・1日2回以上は磨く ・歯ブラシの他にも、フロスを1日1回、 ワンタクトブラシを1日1回は使うのが望ましい |
| 歯茎 |
・ゴシゴシと強くこすらない ・歯と歯ぐきの間に歯ブラシを入れて、そっとマッサージするイメージで |
専門医がお勧めする歯ブラシ・歯磨き粉の選び方
歯ブラシについては、ヘッド部分が小さいものを推奨します。口腔内では、ブラシを動かそうとしても、頬の圧力があったり、あごの骨があったりするために、どうしてもその動きが制限されてしまうものです。ブラシが届かず磨きにい箇所も生じます。
できる限り細かな部分まで磨くためにも、ヘッドが小さいものを使うのがおすすめです。歯ブラシが届きやすく、様々な角度から当てることもできます。できれば柄の部分も薄いものを選べば、口の中でより動かしやすくなります。
また、自分でキレイに磨けない人は電動歯ブラシを使うのもよいでしょう。さらに、歯磨き後に洗口液を使用するのもおすすめです。ただし、日本のメーカーが製造しているものは、洗浄成分が薄いものが多いため、「リステリン」や「コンクール」など海外メーカーの製品がおすすめです。日本のメーカーの先口液でもやらないよりは、やった方がよいので、お家にある場合はぜひ使用してください。
特に歯磨きをしすぎて歯茎を痛めている人は、殺菌効果が期待できるため、使用することをおすすめします。
生活習慣を整える
歯周病を予防するには、免疫力を向上させることも大切です。免疫力が低下すると、細菌に対する抵抗力が弱まるため、歯周病の発症や悪化をしやすくなります。
免疫力を向上させるためにも、以下のことを意識しましょう。
- 栄養バランスを考えた食事を摂る
- よくかんで食べる
- アルコールは適度に摂取する
- 禁煙する
- 質のよい睡眠を十分にとる
- 適度に運動をする
- ストレスを軽減した生活を心がける
口の中の乾燥を防ぐ
唾液には、食べかすを洗い流し、酸を中和したり、細菌の増殖を抑える役割があります。口の中が乾燥し、唾液が少なくなると、細菌が増殖しやすく歯周病になるリスクが高まります。唾液がねばねばした状態になっていれば、口の中が乾燥している証拠です。
次の方法を実践し、改善を試みましょう。
- こまめにうがいをする
- あめやガムを食べる
- 食事はよくかんで食べる
- 保湿ジェルや保湿スプレーを使う
- マウスウォッシュを使う
- 丁寧に歯磨きをする
これらの方法をためしても、なかなか改善せず、気になる場合は、歯科医師へ相談してください。保湿剤や唾液分泌促進薬などを処方してもらうことで、よくなる可能性があります。
適切な噛み合わせを維持する
噛み合わせが悪いと、歯周病の発症や悪化のリスクが高まります。歯や歯ぐきに過剰なストレスがかかるために、歯を支える組織が損傷しやすくなるためです。正しい噛み合わせを維持することは、歯周病予防のために非常に重要です。
もし、噛み合わせの問題が疑われる場合は歯科医師へ相談してください。口腔内の状態を適切に評価のうえ、必要に応じて矯正治療を提案されるかもしれません。歯を適切な位置に調整し、噛み合わせを改善することで、長期的にお口の健康を守れます。矯正の提案をされた場合は、医師と相談しながらよく検討することをおすすめします。
専門医が推奨する!正しい歯磨き方法

歯周病を予防するには、正しく歯磨きをすることが大切です。次のようにブラッシングしましょう。
- 歯と歯ぐきの間に、歯ブラシを45度の角度であてる
- 一度に磨く歯は1〜2本。軽い力で歯ブラシを20回ほど細かく動かす
- 同様に隣の歯を磨く
- 前歯の裏は1本ずつ歯ブラシを縦に当てて磨く
歯磨きは可能であれば、毎食後に行いたいところです。1回あたりの時間は最低でも3分、できれば5分行いましょう。難しい場合は、寝る前の歯磨きを特に丁寧に行うようにしてください。
当院の歯科検診の特徴
体的な数値の提示によって、患者さんに、どれくらいきちんと磨けているのかを実感してもらい、改善意識を高めてもらうという狙いがあります。さらに、鏡をお見せしながら、歯磨き方法の指導も行うので、具体的に改めるべき点もわかります。
口腔内の状態が良好ならその状態の維持が、問題があるなら次回の検診までの改善ができるようお伝えさせて頂きます。
また、当院には、日本歯周病学会より認定を受けた専門医が在籍しています。一般的な歯周病の予防や改善はもちろん、重度の歯周病の治療にも対応しているので、歯周病で悩まれている方はもちろん、気になることがある方は、ぜひ一度ご来院ください。
Contact
ご予約・お問い合わせはこちらから


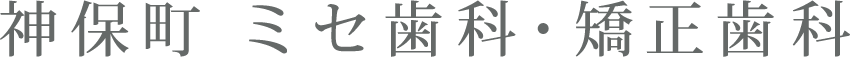
 03-5577-7030
03-5577-7030 WEB予約
WEB予約